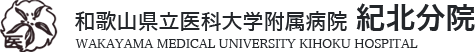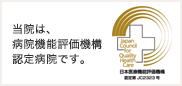華岡青洲の麻酔
全身麻酔が実用化される前の外科手術とは、どのようなものだったのでしょうか。1811年にイギリス聖トーマス病院で膀胱結石の摘出術を受けた患者さんの記録を紹介します。
私は激烈な痛みでショックを受けることに備えていた。痛みを過大評価していたので、切開が始まったとき顔がゆがむことはなかった。しかし、私はこうしたショックに耐えるつもりはないと宣告していた。我慢すればさらに疲労困憊しかねないと確信していたからである。それゆえ、次の瞬間、私は痛みで泣き叫んだ。しかし、断固として手術は続けさせた。
(中略)
結石を引き出すために必要な力が加えられたとき、その痛みは言い表せないほどだった。まるで全臓器が捻られたかのようだった。しかし、この手術で本当につらいところの時間は短かった。「さあ、すべて終わりましたよ」という言葉が耳を打ったとき、「ありがたや、ありがたや」と絶叫が心の奥底に鳴り響き、ほかのことは考えられなかった。この時の感じはまったく筆舌に尽くしがたい。
(WJ Bishop著、「外科の歴史」)
麻酔なしの手術は患者さんにとってまさに地獄の責め苦でした。一方、外科医にとっても痛みに耐えかねて暴れ、泣き叫ぶ患者の手術を続けることは大変なストレスです。痛みのない手術を可能にする麻酔の開発は患者さんだけでなく、外科医にとっても待ち望まれていました。

華岡青洲が開発した麻酔方法は、曼陀羅華(まんだらげ)、別名チョウセンアサガオなど数種類の薬草を配合した麻酔薬「通仙散(つうせんさん)」、別名「麻沸散(まふつさん)」を内服するというものでした。チョウセンアサガオは三世紀頃の中国で麻酔薬として使われていたと言い伝えられていましたが、具体的な配合や使い方に関する記録は何も残っていませんでした。青洲はチョウセンアサガオに数種類の薬草を加え、動物実験だけでなく母於継と妻加恵の協力による人体実験を繰り返し、実に20年の歳月をかけて通仙散を開発しました。そして、1804年(文化元年)10月13日、青洲45歳のときに通仙散による全身麻酔下での外科手術を成功させたのです。近代麻酔の起源とされるウィリアム?モートンがエーテル麻酔下手術の公開実験に成功したのが1846年のことですから、青洲の業績はそれに先立つこと約40年の快挙でした。
さて、皆さんは全身麻酔と聞けば、顔にマスクを当てられ、数を数えているうちに意識がなくなり、次に目が覚めたときは手術が終わっていた、このような情景を想像されるのではありませんか。確かにこのイメージ通りに、現在の麻酔では麻酔薬の注射や麻酔ガスの吸入を組み合わせて、短時間で麻酔状態とし、手術中はまったく痛みをなくし、手術が終わるとすぐに目覚めさせることが可能です。一方、青洲の麻酔はといえば、通仙散が飲み薬であるために麻酔が聞き始めるまでに約2時間、手術を始められるまでに約4時間後、目覚めまでに6~8時間と、現在の麻酔と比べて格段の時間を要するものでした。だからといって、手術に伴う患者の苦痛を和らげることに成功した青洲の偉業の価値が下がるわけではありません。